倉庫現場で「あれ、どこに置いた?」と探す時間が発生したり、とりあえず置いた在庫がいつの間にか行方不明になったりした経験はありませんか?
「ルールを守ってほしい」と注意喚起の貼り紙をしても、結局読まれずにミスが繰り返されることも少なくありません。
業務ルールを作る、システムを導入するという対策は重要ですが時間がかかります。
紛失・行方不明は、致命的な問題なのですぐに防ぐ必要があります。
そこで、お勧めしたいのは「貼り紙」です。
この方法は、私が在庫管理の仕組み作りをする際にもお勧めしている方法です。
貼り紙はルール作りや運用が簡単にもかかわらず、速効性がある方法です。
在庫の紛失は、どんな企業にも起こりうる深刻な問題です。
紛失は単に「担当者の不注意」といった個人の問題ではありません。
管理体制や業務フローといった「仕組み」の問題であることがほとんどです。
この記事では、紛失・行方不明を防ぐ対処的な方法である「貼り紙」の作り方と運用方法を解説します。
そして、そしてそもそも紛失・行方不明が発生する根本的な原因と根本的な解決方法で明日から実践できる具体的な5つの紛失防止対策をステップバイステップで解説します。
探すムダや伝達ミスが劇的に減り、現場スタッフ全員が同じルールで動ける「標準化された倉庫運営」の第一歩を踏み出せます。
目次
在庫紛失を放置する3大リスク
在庫紛失は、単に「モノが1つ無くなった」という問題ではありません。
企業の利益と信用、従業員のモラルを直接的に脅かす、重大なリスクをはらんでいます。
機会損失と顧客信用の失墜
「注文が入ったのにあるはずの在庫が無い在庫がない」という事態は、販売の機会損失であると同時に、「あの会社は在庫管理がずさんだ」という顧客からの信用の失墜に直結します。
キャッシュフローの悪化と資産の減少
在庫は企業の「資産」です。
紛失は資産の減少(棚卸減耗損)を意味します。
私の経験上、紛失・行方不明が日常的に発生している会社では、「また、無いかもしれない」と思って余計に発注する傾向があります。その結果、過剰在庫になってしまい、企業のキャッシュフローを圧迫します。
盗難・持ち出し
紛失・行方不明が当たり前の会社では、従業員による無断での持ち出しも発生している可能性があります。
私が受けた相談の中でもそのような事例が多々ありました。
- 家庭でも使える日用品を扱っている会社では、従業員の無断持ち出しが横行。昔から行われていたため悪いとは誰も思っていなかった。
- 金属を扱う会社では、従業員が金属くずとして金属回収業者に無断に持ち出して現金化していた
- 自社の補修部品が持ち出されて、フリーマーケットサイトに出品されていた
上記のような会社では、従業員が主体となっているため、理由を聞いても「なぜか分からない」と回答されてしまいます。
仮置きは在庫の紛失・行方不明が起こりやすい
これまでの経験上、在庫の紛失・行方不明が起こりやすいのは、在庫の仮置きです。
仮置きが起こりやすい状況は、例えばこんな時です。
- 所定の置き場に置きたいが、量が多すぎておけない。(過剰在庫)
- すぐに出荷・払い出しするので、一時的に置いておきたい
- まだ置き場が決まっていない
仮置きした人は、自分が覚えておけば良いと思っています。
しかし、忘れてしまうこともありますし、他の人が邪魔だと思って動かしてしまうかもしれません。
経験した事例
前日に入荷した500本のタイヤが無く、欠品で現場が止まってしまった。
システム上では入荷したことになっており、入荷担当者は確かに受領した記憶も残っている。
仕入先も確かに出荷しており、空伝票ではないと主張。
入荷担当者が工場の中を探し回ったが見つからず。
色々と探し回った結果、普段置くはずの無い倉庫の裏に500本のタイヤが山積みされていました。
恐らく、入荷で忙しい時間帯だったので他の数名の担当者が邪魔だと、移動を繰り返してしまった結果でした。
何となく動かしているため、誰も頭の中に残っていなかったのです。
システム導入は役に立たない
在庫の紛失・行方不明の防止のために、真っ先に思いつくのが在庫管理システムの導入だと思います。
しかし、「在庫の紛失・行方不明」は、現物管理の問題なのでシステム導入では解決できません。
そこで、お勧めなのが貼り紙の活用です。
貼り紙が効果的
たかが「貼り紙」、されど「貼り紙」ですが、実は非常に有効な紛失防止の手段になります。
実際に私の支援先でも多用している方法で、システムも不要で現場で簡単に運用を開始できます。
ただし、ただ貼り紙をするだけではいけません。
フォーマットを標準化しルールを整備する必要があります。
貼り紙のフォーマットを決める
貼り紙が機能しない理由は、貼り紙のフォーマットが決まっていないからです。
私が現場で様々なフォーマットを試した結果、シンプルで最もうまく機能したフォーマットはこちらです。
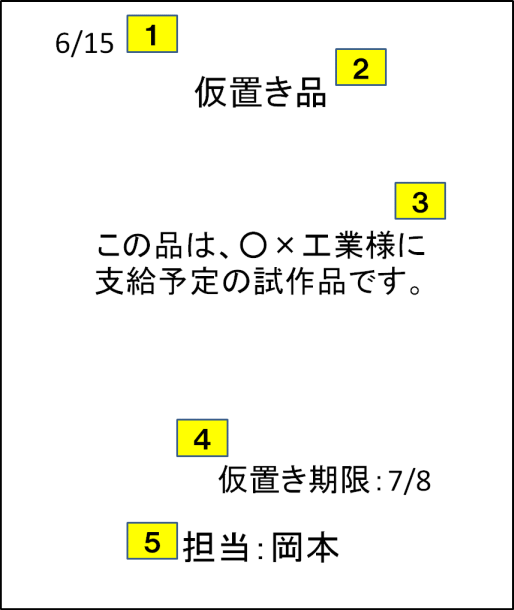
貼り紙を機能させるために必要な5つの項目
貼り紙に、「何を、誰が、いつ、何のために」を網羅することです。それぞれ解説します。
※「必須」項目だけでも問題ありません。
- 日付(必須)
これいつからあるの?
貼り紙された在庫にありがちなことです。
貼り紙をした日付を入れることで、いつからその場所にあるのかを推定することができます。 - 目的
貼り紙をしてその場所に置いている目的を端的に記載します。
「触らないでください」というように注意を促すような記載も効果的です。 - 内容
貼り紙したものがなぜそこにあるのか、理由を書いておきます。
内容を書いておくと、誰が見ても「これは何か、何のためにここに置いてあるのか?」が分かります。 - 期限(必須)
置いた本人が忘れてしまうこともよくあることです。
期限を書いておけば、仮に自分が忘れても期限日を過ぎた貼り紙を見て声をかけてくれる人がいるかもしれません。置き場の近くでいつも作業している人に、「期限が過ぎても来なかったら声をかけてください」と依頼しておくのも効果的です。 - 担当者(必須)
仮置きをした本人の名前を書いておきます。
部署名が書かれていることはよくありますが、部署名だと一体誰が置いたのかが分からず、部署のひとり、ひとりに
聞いて回らないといけないので時間の無駄になります。
この5つを守って貼り紙を作れば、無くなってしまったり、忘れることはほぼありません。
貼り紙の書き方と貼り方
棚や部品の表示と同じように書き方と貼り方は次の2点が重要です。
書き方のポイント
大きな文字ではっきりと濃い色の文字で書く
「現場」で見るものなので、小さな字では見えません。
貼り紙には大きな紙を使用します。(最小でもA5サイズくらいまでにすべきです)
文字は太字の黒マジックではっきりと書きます。
※ボールペンや鉛筆などは線が細く、近づかないと見えません。
貼り紙をする場所
どんなに良い貼り紙を作っても見えなければ意味がありません。
通路から見える場所に貼り付けます。
貼り紙が剥がれないように、しっかりとテープでとめておきましょう。
おすすめはマスキングテープです。
ガムテープやセロテープは剥がすのが大変ですが、マスキングテープは剥がすことを前提に作ってあるので、剥がしやすく、剥がした跡が残らないのも良い点です。
貼り紙の活用は最小限にとどめる
貼り紙の運用方法を解説してきましたが、そもそも貼り紙を多く使わなければいけない現場は、管理できていない現場と言えます。
まずは、整理・整頓を行って、決まったものが決まった場所に決まった量だけ置ける現場をつくらなければいけません。
紛失・行方不明を根本的に無くす方法
貼り紙は、あくまでも「紛失・行方不明」を防ぐ対処的方法として考えておくべきです。
そもそも発生しないようにしなければいけません。
冒頭でお伝えした通り、最初の対処法としてシステム導入はお勧めしません。
2S(整理・整頓)を実施して現場を整備する
まず、実施しなければならないのは、現場整備と状態の維持、つまり2S(整理・整頓)です。
整理の実施
既に置き場が無い状態、モノで溢れている場合は、整理を行いましょう。
「要るモノ」と「要らないモノ」を分ける:まずは使っていないモノ、滞留している在庫を処分・廃棄します。
具体的な整理の進め方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
整頓の実施
根本的に「紛失・行方不明」を無くすためには、「モノの定位置」を決めることが一番重要です。
必要なモノを、誰でも・すぐに取り出せるように置き場所を決め表示します。
整頓の具体的な進め方はこちらの記事で詳しく解説しています。
在庫管理システムの導入
2S(整理・整頓)を行い現場を整備すれば、ようやく在庫管理システムを導入しても機能する状態になります。
紛失・行方不明の多い現場では、各担当者が個別にエクセルで在庫管理をしているケースも多いです。
在庫管理システムを導入して在庫情報を一元管理しましょう。
システム選定で注意するのは、次の2点です。
- 多機能な在庫管理システムを導入しないこと
- 後々、カスタマイズで機能を追加・拡張できるシステムを選ぶこと
多機能なシステムを導入して、複雑で理解できず使いこなせないというケース。
料金最優先で安いクラウド型システムを導入して、業務が高度化してもカスタマイズできず、結局エクセルに頼って属人化するケースがとても多いです。
在庫管理110番では、小さく導入して、自社の習熟に合わせて機能を追加できるシステムを提供しています。
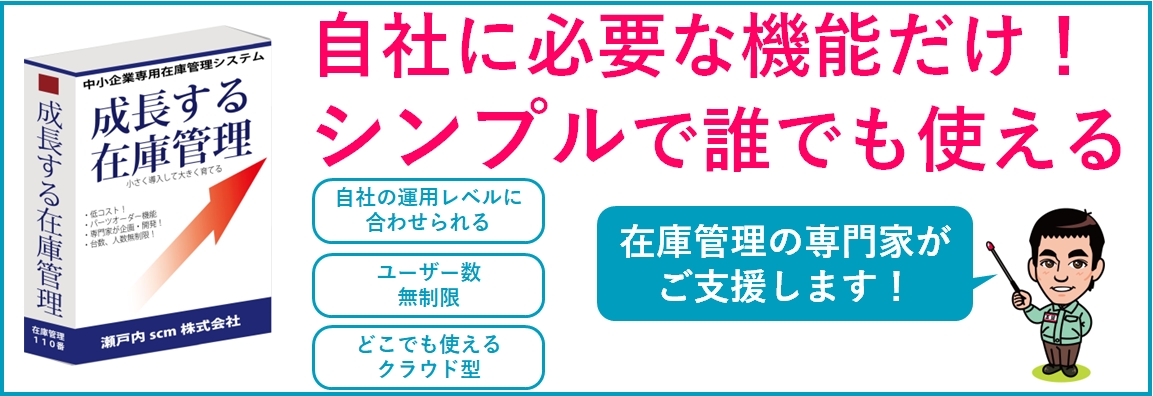
低コストで自社の業務に合ったシステムを導入できる
業務プロセスの標準化
紛失・行方不明が多い会社では、担当者の記憶ややり方に頼った属人化が横行しています。
「誰がやっても同じ結果になる」ように、業務の手順を統一します。
特に標準化・マニュアル化するポイントは以下の通りです。
- 入出庫・検品ルール:作業手順を明文化し、記憶や経験に頼らずに新人でもベテランと同じ作業ができるようにします。
- ダブルチェック体制の構築:ピッキング担当者と梱包担当者を分けるなど、ミスを発見できる体制を作ります。
- 返品・移動処理のルール明確化:イレギュラーな在庫移動こそ、即時処理を徹底します。
在庫管理システムを導入すれば、その人それぞれの属人的な管理は許されません。
業務プロセスの標準化を推進する口実にするのも良い方法です。
貼り紙は「仮置き」に限定する
「仮置き」はあくまでもやむを得ず行うものにしなければいけません。
ただし、自由な仮置きは禁止です。
なぜなら、在庫管理においてどこに置いてあるか分からないのが紛失の一番の原因になるからです。
仮置きは、緊急避難的な対策であり多発する現場は、5Sやロケーション管理が崩壊している証拠であると認識しましょう。
仮置きが発生すると予想される場合はあえて「仮置き場所」を設けておき、その中だけで貼り紙を運用します。
言い換えれば、仮置き場所以外のところに、仮置き在庫は無い状態にするということです。
人の手(アナログ)でも実行可能ですが、大きな労力がかかります。ヒューマンエラーを根本から絶ち、管理を効率化するために、在庫管理システム(WMS)の導入が最も効果的です。
バーコード・ハンディターミナルの活用 商品のバーコードをスキャンするだけで入出庫・検品が完了します。品番の誤認や数量の入力ミスといったヒューマンエラーを限りなくゼロにできます。
リアルタイムな在庫状況の可視化 現場で処理した在庫数が即座にシステムに反映されるため、「情報共有のタイムラグ」が解消されます。事務所にいながら正確な在庫数を把握できます。
システムの導入はコストがかかりますが、紛失による損失、在庫を探す人件費、機会損失といった「見えないコスト」と比較すれば、費用対効果は非常に高いと言えます。
まとめ
倉庫内での在庫の紛失や行方不明を防ぐため、「貼り紙」の作り方と運用のコツを解説しました。
貼り紙のフォーマットと運用ルールを標準化すれば、立派な紛失防止ツールになります。
具体的には、効果的な貼り紙に必要な「日付」「目的」「内容」「期限」「担当者」の5項目を明記すること、そして「太い黒マジックで書く」「すぐ見える位置に貼る」といった視認性を高める工夫が必要です。
ただし、貼り紙は最小限にとどめるべきです。根本的な解決策の要点は以下の3点です。
- 5S(整理・整頓)の実施による現場整備(どこに、何があるかが誰にでも分かる置き場にするため)
- 在庫管理システムの導入(在庫の一元管理)
- 業務プロセスの標準化(脱、属人化)
定期的に棚卸を実施して在庫の精度を確認する
これまで解説した2S、在庫管理システムの導入、業務プロセスの標準化が、キチンと機能していれば紛失・行方不明は起こらなくなります。
まだ行方不明や紛失が発生していたり、ズレがあるかどうかは棚卸で在庫精度を確認します。
「実在庫」と「帳簿在庫」の照合:実際に倉庫にある在庫(実在庫)を数え、データ上の在庫(帳簿在庫)との差(棚卸差異)を洗い出します。
まだ在庫合わない場合は「数が合わなかった」で終わらせてはいけません。
棚卸差異分析を実施します。
「なぜ差異が出たのか(入力ミスか、ピッキングミスか、正しい置き場に無かったのか、盗難か・・・)」を分析して、2S(整理・整頓)、プロセス標準化にフィードバックします。
在庫管理110番では、棚卸改善セミナーを行っています。
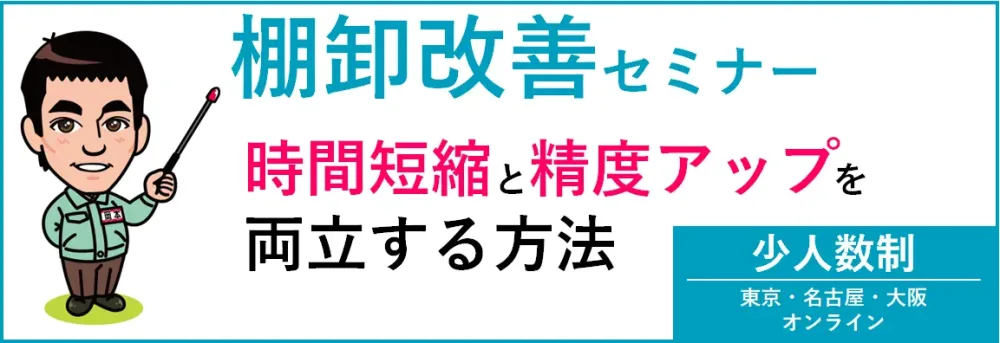
棚卸時間の短縮ややり方だけではなく、紛失・行方不明の予防につながる棚卸の精度アップ、差異分析の方法も解説します。
実際のコンサルティングの現場で成果が出たノウハウを惜しみなくお伝えします。
受講者特典をご用意しています
在庫管理に関するご相談・お問合せ
在庫管理110番では、在庫管理に関するご相談・お問合せを随時受付中です。
現場改善、システム導入等、在庫管理に関して総合的にサポートしています。
ただいま、在庫管理アドバイザーによる無料の個別相談を実施中です。