結論:販売管理システムの在庫管理はあくまでも簡易的、複雑な在庫管理は在庫管理システムが不可欠です。
大部分の企業が、まず初めに導入するのは会計システムです。
2番目に選択されることが多いのが販売管理システムです。
販売管理システムには、在庫管理機能がついていることが多いため、「売上も請求も、そして在庫も一元管理できる」と考えるのではないでしょうか?
- 倉庫のどこに何があるか分からず、出荷作業にベテランの勘が必要な状況は変わらない
実際に、在庫管理110番にも次のようなご相談をいただいています。
- 最初はうまくいっていたが、商品数が増えてくると思うように管理ができなくなった
- 結局、Excelでの二重管理から抜け出せない
- 販売管理システムで在庫を管理しているが限界を感じた
- 簡易的な在庫管理しかできないため、在庫が合わない
もし、あなたがこの記事を読んで少しでも思い当たる節があれば、それはあなたの会社のやり方が間違っているわけではありません。むしろ、多くの企業が販売管理システムによる在庫管理で陥りがちな、想定内の課題であり、当然の結果です。
なぜ、販売管理システムの在庫管理機能は「期待はずれ」に終わることが多いのでしょうか。
その理由はシンプルです。販売管理システムと在庫管理システムでは、そもそも作られた「目的」が全く違うからです。
この記事では、両システムの本質的な違いから、販売管理システムだけでは解決できない在庫管理の限界、そして、企業の成長と利益を最大化するための最適なシステム選定の考え方まで、具体例を交えて徹底的に解説します。
目次
販売管理システムと在庫管理システムの役割の違い
多くの人が誤解しがちなポイントですが、販売管理システムの主目的は、販売活動に関する「お金の管理」です。
システムの基本設計として「モノの管理」を完璧に行うように作られていないため、構造的な無理が生じます。
販売管理システムの役割
その名の通り、主に売上や販売に関する商流を管理が目的です。
- 機能:お金の流れ(見積、受注、売上、請求、入金)を正確・効率的に記録・管理するための機能が充実しています。
- 管理する情報:「いつ、誰に、何を、いくらで売ったか」という売上に関する取引情報。
在庫管理システムの役割
一方、在庫管理システムは、モノの管理=物流管理が主目的です。
- 機能:モノの流れ(入荷、検品、保管、ピッキング、出庫)を正確かつ効率的に管理するための機能が充実しています。
- 管理する情報:「どの商品が、今、倉庫のどこに、何個、どんな状態で保管されているか」という物理的な情報。
このように、販売管理システムにとっての在庫は、売上ですが、在庫管理システムにとっては「物理的な商品(モノ)」です。この視点の違いが、機能の限界となって現れるのです。
補足
モノを管理するシステムには、在庫管理システムのほかに倉庫管理システムがあります。
似ていますが、役割が少し違います。特徴を簡単にまとめると次の通りです。
- 倉庫管理システム:倉庫内の業務を効率化するため「モノの保管と移動」を管理するシステム(ピッキングなどの荷役や保管、移動に特化)
- 在庫管理システム:企業の利益を最大化するため「モノとお金の流れ」を管理するシステム(上記のほか、発注や在庫金額の管理等も含むことが多い)
もっと詳しく知りたい場合はこちら↓
5分で解決】在庫管理と倉庫管理の違いとは?業務内容からシステム選定方法まで徹底解説
多くの企業が陥る「販売管理システムの在庫管理機能」の限界
この役割の違いから、販売管理システムでは対応しきれない、在庫管理の限界が生まれます。
販売管理システムは「商品Aが100個ある」という数量は管理できても、「その100個が倉庫のどの棚に、いつ入荷されたものか」といった状態まで管理するのは非常に苦手です。
ロケーション管理
どこに何があるかを管理できないため、倉庫内でのピッキング作業は、結局ベテラン作業員の経験と勘に頼ることになります。新人は即戦力になれず、業務の属人化が進みます。
ロット管理・使用期限管理
同じ商品であっても、食品や化粧品、医薬品などでは期限や製造ロット番号が重要です。
同じ商品を別物として管理するために必須となる「ロット番号ごとの管理」ができないため、期限の古いものから先に払い出していく、「先入れ先出し(FIFO)」の徹底が困難です。
これにより、気づかぬうちに使用期限切れの在庫を出荷してしまった、在庫はあるけど期限が切れているので売上機会の損失といった、重大な信用問題に発展するリスクを抱えます。
ピッキング指示書
見積書や請求書の作成はできますが、「どこに・何が・どんな状態で」といった場所や期限を考慮したピッキング指示書が作れません。
したがって、シングルピッキングやトータルピッキングといったように、効率を考えたピッキング指示を出すことができず、倉庫内を探し回らなければならず、倉庫作業が属人化・ベテランに集中してしまい非効率になりがちです。
(主なピッキング方法はこちらの記事で解説しています:ピッキング方法と作業の効率化(精度と時間短縮を実現))
引き起こされる深刻な経営課題
これらの限界は、単なる「現場の不便」では済みません。
気づかぬうちに、会社の利益を蝕む深刻な経営課題へと直結していくのです。
- 隠れ欠品による販売機会の損失:システム上は在庫があるのに、倉庫のどこにあるか分からず「欠品です」と答えてしまう。
- 不明瞭な在庫によるキャッシュフローの悪化:不要な在庫がいつまでも倉庫に滞留し、会社の資金繰りを圧迫する。
- 倉庫作業の非効率化と人件費の高騰:属人化した作業、探し回る時間、手作業によるミスが、無駄な残業代や人件費となって経営に重くのしかかります。
【機能比較表】一目でわかる!できること・できないこと
見積・請求◎×販売管理システムの本来の役割
| 機能 | 販売管理システム | 在庫管理システム | 違い |
|---|---|---|---|
| 在庫数の把握 | 〇 | ◎ | 販売管理システムは、主に販売数。在庫管理システムは仕入れから販売まで |
| ロケーション管理 | △ | ◎ | 販売管理システムは会社内にいくつあるか?在庫管理システムは「何が、どこにあるか」が管理可能 |
| ロット・使用期限管理 | × | ◎ | 鮮度・期限管理には必須。 |
| 複数倉庫・多店舗 | △ | ◎ | 在庫管理システムだと拠点間の在庫移動や効率的なピッキングが可能 |
| 在庫数一元管理 | × | ◎ | 一か所で増減した在庫数を反映・一か所で確認できる |
販売管理システムで「できる」在庫管理のチェックリスト
販売管理システムは「簡易的な在庫管理機能」を持っているため、あなたの会社の状況によっては在庫管理システムが不要かもしれません。
そこで、販売管理システムによる在庫管理で十分な会社に該当するかどうかが分かるチェックリストを作成しました。
- 扱っている商品点数(SKU)が100点以下
- 商品の販売チャネルは1か所だけ
- 在庫の保管場所は1ヶ所で、倉庫も小規模
- ロット管理や使用期限管理が不要な商材を扱っている
- 従業員数が5名以下で、全員が在庫情報を把握できる状態
- 多少の在庫のズレがあっても経営に影響がなく、在庫管理の目的は会計上の数字の把握で十分
在庫管理システムを導入すべき会社の状態チェックリスト
在庫管理110番には、販売管理システムによる在庫管理は、最初はできていたけど限界が来た。というご相談がとても多いです。
(次のリストで2つ以上当てはまる場合、在庫管理システムの導入を強く推奨します。
- 在庫数が合わないことが頻繁にあり、欠品や過剰在庫が多発している
- ECサイトと実店舗など、複数の販売チャネルを持っている
- 商品点数が多く管理が複雑
- ロット管理や先入れ先出しが必須の商材を扱っている
- 倉庫作業の属人化・ベテラン頼りを解消し、パート・アルバイトでも同じ品質で作業できるようにしたい
- 今後、事業を拡大していく計画がある
在庫管理システムを導入することで、無駄なコストの削減・キャッシュフローの改善が見込めるため、売上機会の損失を予防し、さらに大きな利益を得られる可能性が非常に高いでしょう。
販売管理システムと在庫管理システムの連携
在庫管理システムを導入する場合は、既存の販売管理システムとデータ連携できるものを選択しましょう。
システムはデータ連携といって、各システムの情報をお互いに行き来させ、各システムの強みを生かし弱みを補い合い、相乗効果が見込めます。
在庫管理システムからの正確な在庫数を元に、販売側は機会損失なく販売活動に集中。
販売管理システムからの正確な販売実績を元に、倉庫側は最適な発注計画を立て、効率の良い倉庫作業を実現し、過剰在庫を削減とキャッシュフローの向上に貢献しさらなる売上のアップに役立ちます。
事業の成長と利益の最大化を目指すなら、専門の在庫管理システム導入を検討すべき
従業員数5名以下、商品点数100点以下、保管場所が目の行き届く環境の場合は、販売管理システムによる在庫管理で十分です。
しかし、創業期を過ぎ、事業が成長フェーズに入った企業にとって、専門の在庫管理システムへの投資は、もはや「コスト」ではなく、未来の利益を生み出すための「戦略」です。
正確な在庫管理は、機会損失を防ぎ、キャッシュフローを改善し、顧客満足度を高め、企業の競争力を直接的に強化します。
一度、トラブルが起こってしまうと、売上機会の損失、クレーム対応、滞留在庫によるキャッシュフローの圧迫、さらに保管費用の増大など、簡単に解消できない慢性的な問題を引き起こします。
理想形は「販売管理システム」と「在庫管理システム」のデータ連携
「では、販売管理システムは不要なのか?」というと、そうではありません。理想的なのは、それぞれの得意分野を活かす「システム連携」です。
- 在庫管理システムで、正確なモノの流れ(実在庫)を管理する。
- 販売管理システムで、正確なお金の流れ(売上・請求)を管理する。
そして、両者をAPIやCSVなどでデータ連携させ、受注情報が自動で在庫管理システムに渡って出荷指示が出され、出荷実績が自動で販売管理システムに渡って売上計上される、という仕組みを構築するのです。
これにより、両システムのメリットを最大限に享受し、バックオフィス業務全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現できます。
まとめ:『なんとなく』の在庫管理から脱却し、攻めの経営基盤を築こう
この記事では、多くの企業が陥りがちな「販売管理システムの在庫管理機能」の限界と、その解決策について解説してきました。最後に、重要なポイントを振り返りましょう。
販売管理システムの在庫管理機能は、あくまで「販売活動に付随する簡易的な機能」です。
販売管理システムと在庫管理システムは、その目的が根本的に異なります。この違いを理解しないまま販売管理システムだけで在庫を管理しようとすると、事業の成長と共に必ず壁にぶつかります。
- 役割の違い:販売管理は**「お金の流れ」、在庫管理は「モノの流れ」**を管理する。
- 機能の限界:販売管理システムでは、物理的な在庫の状態(ロケーション、ロット等)や、倉庫現場の作業効率化には対応しきれない。
- 理想の形:それぞれのシステムの専門性を活かし、APIなどで両システムを「データ連携」させることが、バックオフィス業務全体のDXを実現する鍵となる。
自社の業務にフィットし、柔軟なシステム連携ができる在庫管理システム
この記事の冒頭で触れた、「販売管理システムを導入したのに、在庫管理がうまくいかない…」という「こんなはずではなかった」という悩み。
それは、既存のパッケージソフトが、あなたの会社の独自の業務フローに完全にはフィットしていない証拠なのかもしれません。
多くの在庫管理システムは多機能を売りにしていますが、自社の特殊なルールや将来の事業展開に合わせきれず、「帯に短し襷に長し」な状況に陥りがちです。
しかし、もし「あなたの会社の業務に100%フィットする在庫管理システム」を、実務を知る在庫管理の専門家と共にゼロから構築できるとしたらどうでしょうか。
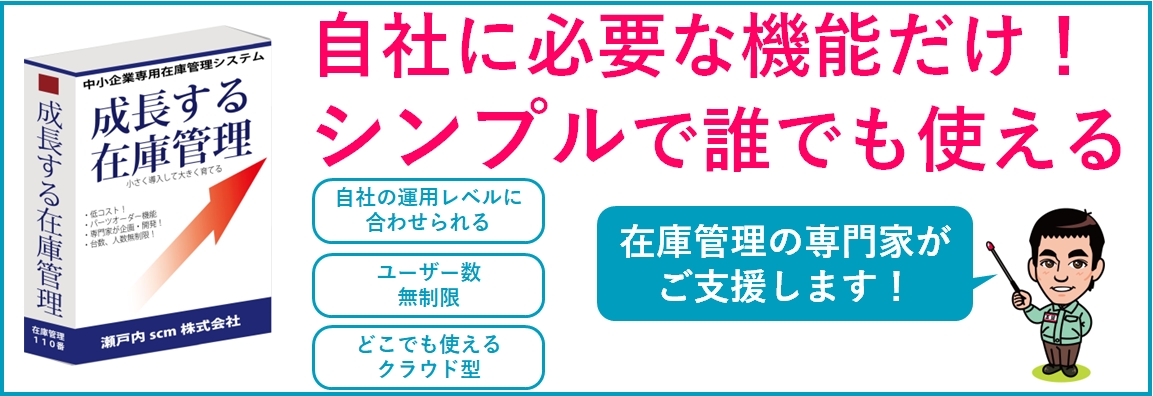
在庫管理110番が開発した成長する在庫管理システムは、単に在庫管理システムを提供する会社ではありません。
これまで500社以上の在庫管理の相談にのってきた、在庫管理のスペシャリストです。
お客様の業務を深くヒアリングして、その流れそのものを「仕組み化」することで、根本的な課題解決を目指します。
本記事で解説した「販売管理システムとの理想的なデータ連携」はもちろん、貴社独自の複雑なロット管理や複数倉庫の運用ルールにも完全対応した、本当に使いやすく、事業の成長に合わせて進化し続けるシステムを丁寧に構築します。
もし「パッケージソフトでは、うちの課題は解決しきれないかもしれない」と少しでも感じたら、ぜひ一度、私たちの成長する在庫管理をご覧ください。貴社のビジネスを次のステージへ引き上げる、本当の「仕組み」がそこにあります。
低コストで自社の業務に合ったシステムを導入できる
【事例】在庫管理システムの導入で、売上と利益を向上させた例
弊社の成長する在庫管理の導入例をご紹介します。
中古品販売:原価管理で適切な値決めができるように
導入前の悩み・課題
在庫管理システムとしてサブスクの在庫管理アプリを使用し、入出庫やスマートフォンでの入庫や在庫確認もできるので便利。
しかし、同じ商品でも1品1品、仕入金額が仕入先や購入日により頻繁に変動するため、在庫原価金額をする必要があった。
そのため、現在庫の平均原価金額を計算するため在庫管理アプリからエクセルに抽出して、自力で計算するような方法をとっていたが限界を感じた。
導入後
自動で平均原価を計算できるようになり、適切な販売価格を付けられ、思ったように利益を確保できるようになった。
現場の負担も増えず、混乱なくスムーズに導入できた。
詳しくはこちらをご覧ください。
雑貨販売:在庫の一元管理による注文数の増加
導入前
複数のECサイトと卸売りで雑貨を販売しています。
ECの在庫管理の一元管理に特化したサブスク型の有名なシステムを導入しました。
卸の方の同期はできなかったのですが、当初はECと卸の在庫を振り分ければよいと思っていたのですが、ある時点からどちらの在庫を信じて良いかわからなくなって・・。
結局手間が導入前と後で全然変わらず使うのをやめました。
導入後
一番の課題だった現在庫の把握ががすごくスピーディにできるようになったのが一番大きいです。
例えば、卸先の営業さんから、「急遽売り場に棚を作ることになったので、「iphoneの○○シリーズの在庫数をとりあえず今ある分だけ全部出してほしい」というご依頼がたまにあります。
以前だと、そのような問い合わせを受けても、どうやっても在庫確認と用意で1~1日半くらい時間がないと対応できませんでした。
しかし、システム導入で最新の現在庫がスピーディーに確認できるようになり、以前のように時間をかける必要がなくなりました。
急な要請でもうろたえずに、取引先とのスピーディなやり取りの流れができるようになりました。
その結果、お客様からは早い対応ができるという評価をいただき、信頼度が高まりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
今こそ、自社の在庫管理レベルを正しく診断し、未来の成長を見据えた戦略的なシステム投資を行うべき時です。
「お金」と「モノ」それぞれのプロフェッショナル(専門システム)に仕事を任せ、それらを強固に連携させること。それこそが、企業の競争力を高め、厳しい市場を勝ち抜くための最適解なのです。
