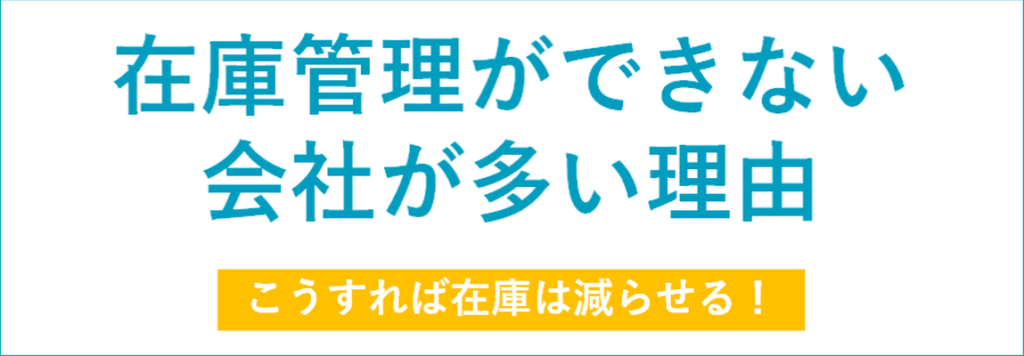「在庫管理がどうしてもうまくいかない…」「数え間違いや入力ミスが多くて困っている…」「過剰在庫や欠品が全然減らない」、結局「何から手をつければいいのか分からない…」
在庫管理に対して、そんな苦手意識や課題を抱えていませんか? 在庫管理は多くの企業にとって重要ですが、同時に複雑で手間がかかるため、苦手だと感じる方が多いのも事実です。
一方で、在庫管理がキチンとできている会社もあるのが事実です。
この記事では、在庫管理が苦手だと感じる主な原因を掘り下げ、多くの企業が陥りがちな失敗パターンを解説します。
さらに、効率的で正確な在庫管理を実現するための具体的な解決策や、改善に役立つ考え方、ツールの選び方まで詳しく解説します。
この記事を読めば、なぜ在庫管理がうまくいかないのかが明確になり、あなたの会社が今抱えている課題に合った改善策を見つけるヒントが分かります。
在庫管理の苦手を克服、在庫管理の基本が学べる
目次
在庫管理が苦手なのはあなたの会社だけではない、でも放置は超危険
まずお伝えしたいのは、「在庫管理が苦手だ」と感じているのは、決してあなたやあなたの会社だけではないということです。多くの担当者や経営者が、在庫管理の煩雑さやプレッシャーに悩んでいます。
しかし、「苦手だから」と現状の課題を放置してしまうと、気付かないうちに会社の経営に深刻な影響を与えかねません。
危ないと気づいたときに、直そうとしても簡単には直りません。
なぜ在庫管理は「苦手」だと感じやすい5つの原因
在庫管理が「苦手」と感じられる背景には、いくつかの共通した原因があります。
ルールが曖昧・整備されていない
「誰が」「いつ」「何を」「どこに」「いくつ」動かしたのか、正確に記録・共有する仕組みがない状態です。
入庫・出庫・保管場所などのルールが明確でないと、担当者によってやり方や判断が異なるのでと、ミスや混乱が生じやすくなります。特に、ベテランに頼っていたり、口頭での指示や暗黙の了解に頼っているケースは要注意です。
アナログ管理の限界
紙の在庫管理表やExcel(エクセル)での管理は、手軽に始められる反面、入力ミス、計算間違い、情報のリアルタイム性の欠如、複数拠点での情報共有の難しさといった問題が発生しがちです。
取り扱い部品(商品)の点数が増えれば増えるほど、管理が煩雑になり、ヒューマンエラーのリスクが高まります。
担当者任せになっている(属人化)
特定の担当者しか在庫状況を把握しておらず、その人がいないと業務が滞る「属人化」の状態です。
担当者の勘や経験に頼った管理は、客観的なデータに基づかないため、過剰在庫や欠品のリスクを高めます。
属人化の状態下では、担当者の異動や退職時に引き継ぎが困難になり、せっかくのノウハウが受け継がれずまた最初からやり直しになるため、効率も低下します。
在庫管理の重要性への認識不足
なぜ、在庫管理が重要なのか?経営層や現場の担当者が、在庫管理の目的(欠品防止、過剰在庫削減、キャッシュフロー改善など)や、その失敗が経営に与える影響を十分に理解していないケースです。
「ただ数を数える作業」と捉えられていると、改善へのモチベーションが生まれにくくなります。
在庫管理システムのミスマッチ・活用不足:
在庫管理システムは導入がゴールではなく使いこなすことがゴールです。
在庫管理システムを導入していても、自社の業務フローに合っていなかったり、機能が複雑すぎたりして、うまく活用できていない場合が非常に多いです。
また、導入することがゴールになり、データの入力やマスタのメンテナンスが徹底されていないケースも見られます。
在庫管理の放置が招く4つの共通する問題
在庫管理は企業の収益性や競争力に直結する重要な課題です。
単なる「苦手」では済まされません。在庫管理に問題を抱えている会社には、次のような問題を抱えているという共通点があります。
欠品による機会損失
お客様が欲しい時に商品がなく、販売機会を逃してしまう(売上ダウン)。
- 在庫の精度が悪くあるはずのものが無い
- 他の会社の予約品(引当品)を間違って出荷してしまった
- 発注していたと思ったらやっていなかった
- いつも納期遅ればかりだ
こんなことが続くと、
「あの店はいつも品切れだ、納期も守れない」と思われ、顧客からの信用を失います。
急いで仕入れることになり、通常より高いコストがかかる場合もあります。
キャッシュフロー(お金の流れ)の悪化
仕入れに使うお金は、会社で日常的に使う50~80%と圧倒的な多さです。
仕入れすぎの過剰在庫、売れずに残り続けている不良在庫が増えると、仕入れに使ったお金が現金として回収できず、会社の資金繰りが苦しくなります。
管理コストの増大
倉庫が整頓されておらず、どこに何があるか分からず、在庫を探すのに余計な時間がかかるようなります。
在庫の数が合わないため、棚卸で何度も数え直したり、原因を調査したりする手間が増える。
ミスを発見・修正するための人件費がかさみます。
在庫が増えると、保管や管理のため倉庫や人を増やすことになり、管理コストが増加します。
経営判断の遅れや誤り
正確な在庫数が分からないため、どれくらい仕入れるべきか、どれくらい生産すべきかといった計画を適切に立てられず、作りすぎ・買いすぎが起こりやすくなり、結果的に過剰在庫につながります。
また、正確な在庫が分からないと、正確な利益が計算できないため、間違った経営判断をしてしまうリスクがあります。
これらのリスクは、一つひとつは小さく見えても、積み重なると会社の利益を大きく損ない、経営そのものを危うくする可能性があります。だからこそ、「苦手」だとしても放置せずに改善に取り組むことが重要なのです。
苦手克服!在庫管理を改善するための具体的なステップ
在庫管理を改善する具体的なステップを紹介します。
目標を決める
社長が「在庫を減らせ!」というだけでは、従業員は「今の状態が適正だ」と思っているので、動いてくれません。
在庫管理110番にお寄せいただくお悩みでも、
- 社長や経営陣:在庫を減らしてほしいけど、一体どれくらいがうちの会社の適正値かがわからない
- 管理職や担当者:在庫を減らせと言われているが、具体的にどれだけ減らせばよいか分からない
あなたの会社としての、適正在庫金額を示さなければいけません。
- 何をすべきか:会社としての在庫削減の目標金額、または目標の在庫金額を決める
- ポイント:経営でも現場でも通じる共通の管理指標であること
在庫管理110番では、自社の適正な在庫金額が計算できる在庫管理セミナーを定期的に実施しています。
在庫の精度向上
- やるべきこと:在庫の精度が高いことは、在庫管理の基本中の基本です。自社の在庫精度の確認は、実地棚卸で行います。
- ポイント:なぜ差異が発生したのか原因を分析し、再発防止策を講じることが、管理精度向上の鍵です。
在庫管理110番では棚卸改善セミナーで、短時間で精度を上げるための棚卸のノウハウを提供しています。
コンサルティングの現場で実証済みのノウハウです。この通りにやれば、必ず在庫精度は向上します。
棚卸改善セミナー【時間短縮と在庫精度向上を同時に実現できる方法】
在庫管理ルールの明確化と標準化
- やるべきこと:入出庫の手順、保管場所のルール(ロケーション管理)、責任者、記録方法などを明確に定め、マニュアル化します。誰がやっても同じ結果になるように標準化することが目標です。
- ポイント:まずやるべきことは現品管理、その中でも重要なのは2S(整理・整頓・清掃)です。在庫が見やすく、取り出しやすい環境を整えることが第一歩です。
現品管理について体系的に学びたい場合は、在庫管理の教科書01「現品管理」に詳しくまとめています。
現状の可視化と課題の特定
- やるべきこと:過剰在庫、滞留在庫、欠品しやすい品目などを洗い出します。
- ポイント:大量にある品目を全て実施する必要はありません。ABC分析(重要度に応じてランク分けする手法)を活用し、対策や管理の優先順位をつけます。
在庫管理システムの導入・見直し
- やるべきこと:エクセルによる管理に限界を感じている場合はシステムの導入、現在のシステムが業務に合っていない、使いこなせていないと感じる場合は入れ替えを検討します。
- ポイント:自社の規模、業種、扱う在庫の種類、予算、既存システムとの連携などを考慮し、最適なシステムを選びましょう。いきなり高機能なシステムを導入するのではなく、スモールスタートがベストです。
在庫管理システムの導入失敗は本当に多いです。システム会社の営業に乗せられて選定するのは絶対にやめましょう。
在庫管理システム成功の手引き|中小企業が導入・入替の失敗を防ぐ方法
担当者の教育と意識向上
- やるべきこと:在庫管理の重要性や、定められたルール、システムの使い方について、担当者への教育や情報共有を徹底します。
- ポイント:在庫管理は特定部署だけの問題ではなく、営業、製造、購買など、関連部署との連携が不可欠であることを伝え、全社的な協力体制を築くことが理想です。
在庫管理110番が開催している在庫管理セミナーは、これまで350名以上が受講しています。
在庫管理の教育にも活用されており、大変好評です。
自社の在庫管理レベルを知る
ここまで、在庫管理を改善する具体的なステップを解説しました。
しかし、在庫管理ができていないといっても、会社によってそのレベルは様々です。
様々な課題があったとしても、在庫管理のレベルによってやるべきことは決まっています。逆に言えば、今やってはいけないことも決まっています。
在庫管理110番では、あなたの会社の在庫管理レベルを診断するチェックシートを無料で配布しています。
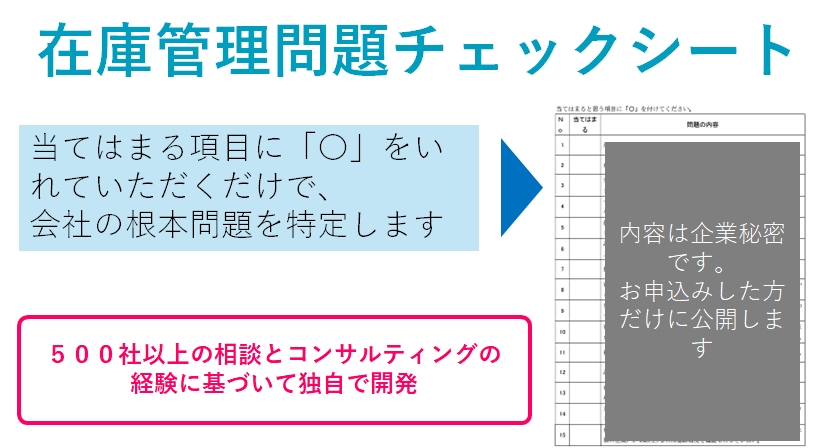
自社の在庫管理レベル、そしてあなたの会社が何から取り組めば良いかがわかります。
まとめ
在庫管理が「苦手」だと感じる背景には、次のような問題が潜んでいます。
- ルールの未整備
- アナログなエクセル管理の限界
- 属人化、
- 重要性の認識不足
- 在庫管理システムのミスマッチ、使いこなせていない
しかし、これらの原因を一つひとつ理解し、適切な対策を講じることで、苦手意識を克服し、効率的で正確な在庫管理を実現することは十分に可能です。
まずは、自社の現状を把握し、どこに課題があるのかを特定することから始めましょう。そして、ルールの整備、ツールの見直し、定期的な棚卸し、担当者の意識向上といった改善策を、できるところから少しずつ実行に移していくことが大切です。
正確な在庫管理は、無駄なコストの削減、キャッシュフローの改善、顧客満足度の向上に繋がり、ひいては企業の競争力強化に貢献します。この記事を参考に、ぜひ在庫管理改善への一歩を踏み出してください。
在庫管理を学ぶ
在庫管理110番では、在庫管理を学ぶ場として、様々なテーマをご用意しています。
適正在庫や棚卸、販売計画、下請法まで・・・
- 今の自分達のやり方が正しいかどうかが分からない
- 従業員に在庫管理を学んでほしい
- ずっと昔から悩んでいる課題がずっと解決できない。
在庫管理110番が開催しているセミナーはこちらからご覧いただけます
在庫管理に関するご相談・お問合せ
在庫管理110番では、在庫管理に関するご相談・お問合せを受け付けています。実務をよく知る在庫管理システムの専門家があなたのお悩みを解決します。
【無料】在庫管理個別相談受付中です!